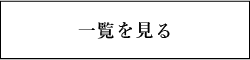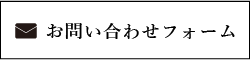京都でお墓を建てるための基礎知識
「京都でお墓を建てたいけれど、どうしたらいいの?」そんな疑問をお持ちの方へ、建墓のながれや注意点をまとめました。
♦お墓を建てる流れ
1.墓所(お墓を建てる場所)を決める
京都でお墓を建てるには、まず墓地を決める必要があります。墓所には、宗派に合わせた寺院墓地のほか、宗派にこだわらずに利用できる民間墓地、公営墓地があります。
1.寺院墓地:お寺が管理する墓地。宗旨宗派が決まっている。
2.民間墓地(霊園):民間会社や社団・財団法人が経営する墓地。宗旨宗派問わない。宗教法人が管理。
3.公営墓地:地方自治体が管理する墓地。宗旨宗派問わない。
石茂では、京都を中心とした墓所のご紹介をしております。見学のご予約も可能です。霊園・墓地の一覧はこちらをご覧ください。
お墓参りをしている実家があっても、将来その墓所に入れるとは限りません。別の墓所を設ける必要がある場合も。ご家族とよく相談された上で、進めてください。

2.墓地の区画を示す「巻石」を設置する

巻石とは、お隣のお墓との境界を示す石です。墓所を購入する際に既に設置されている場合もありますが、ない場合は、早めの設置がおすすめです。
京都では、墓所の区分を1聖地単位(900㎜×900㎜)で決められています。購入された墓所の大きさに合わせて巻石を設置します。高さや使用する石材は、周りのお墓との調和も考慮して考えることが多いです。
墓所によっては、墓地の契約後、〇年内に巻石や墓石の建立を求める規約もありますので、ご注意ください。
3.墓石を選ぶ
墓石は、国内産から外国産まで様々な種類があります。店頭でじっくりと実物を見て、お客様にとっての最良の石をお選びください。ショールームのご見学は、事前のご予約がスムーズにご案内できます。
墓石が決定したら、文字や家紋の彫刻内容を相談し、建立日を決めます。お墓を建てる日は、四十九日や百か日など、ご法要日の1~2週間前が一般的です。お性根抜きやお性根入れなど、お寺様のご都合も伺いながら、相談してお決めください。そして法要の際に、開眼供養とご納骨を行っていただきます。

♦よくあるご質問
1.お墓はいつ建てればいいの?
最近亡くなられた場合は、「四十九日」の忌明け、または、「百か日」か一周忌までが一般的です。新仏さまのご納骨が伴わない場合は、お彼岸やお盆などのタイミングで建てることが多いです。
2.どれくらいの大きさのお墓がいいの?
京都市内では、1~4聖地の大きさの場合、8寸角が最も多いです。郊外や村墓になると、9寸や1尺の大きなお墓が好まれます。周りのお墓との調和を見ながら決められると安心です。
3.正面には何と彫る?
一般的に、ご家族のお墓の場合、正面文字は「〇〇家之墓」「〇〇家先祖代々之墓」、或いは、宗派ごとのお題目を彫り、霊標かお石碑の正面向かって右側面に「戒名・俗名・没年月日・行年」を入れることが多いです。周りのお墓がどのような文字を彫られているかも確認して、お寺様に相談されることをおすすめします。
4.京都では、お骨はどのような形で埋葬するの?
関西では、お骨が土に戻るように、さらしの袋に入れ替えて埋葬するのが一般的です。納骨のお手伝いもできますので、お気軽にお問い合わせください。
5.開眼供養とは?
新しくお墓を建てるときや、再建をするときには、開眼供養を行います。新しいお石碑に、仏様の魂を宿す為の儀式です。「お性根入れ」「お魂入れ」とも呼ばれます。
6.生前にお墓を建ててもいいの?
はい、大丈夫です。生前にお墓を建てることを「寿陵(じゅりょう)」と言います。中国では、生前墓を建てることは、縁起が良いとされ、その影響で建てられる方も多いそうです。日本においても、生前に建てたお墓は相続時の税金対象外となることや、ご家族へのご負担を考慮して生前に建てられる方は多いです。生前にお墓を建てると、ご自身のお墓を納得がいくまで考えて、安心して建てることができます。
♦京都でのお墓づくりはご相談ください
本コラムでは、京都でお墓を建てる上での基本的なお話をしました。その他、ご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。