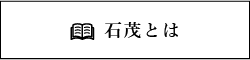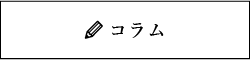【石燈籠】歴史と魅力
♦石燈籠のはじまり
石灯籠は、仏教の伝来と共に、その文化や加工技術が日本に伝わりました。元々は、仏前で灯りを供えるためのものでした。当時、火はとても神聖なものとして信じられていたのです。やがて、神社にも用いられ、灯りを灯す役割だけでなく、神仏の荘厳さを引き立てる存在となりました。

奈良時代から平安時代の初期には、奈良・薬師寺東塔や京都宇治・平等院鳳凰堂のように、建物正面の中央に一基だけ置かれる形が一般的でした。
しかし桃山時代初めごろから、一対で立てる形式がはじまり、鎌倉時代の仏教興隆期には多くの灯篭が造られました。仏教信仰が武家や庶民へ広まるとともに、寺社の参道にずらりと灯篭が並ぶ景観が生まれました。
♦茶の湯と灯篭

安土桃山時代、茶の湯文化が深まる中で、灯篭は日本庭園の重要な景物としても用いられ始めます。
千利休が初めて庭に灯篭を取り入れたと言われており、江戸時代には、雪見灯篭や織部型、岬型など独自の形へと発展しました。
やがて庶民の庭にも広がり、京都の町屋の小さな坪庭にも灯篭が置かれるようになります。
♦燈篭の形
石灯籠は大きく「立ち型」と「置き型」に分かれます。
立ち型(基本形)
上から順に、「宝珠」、「笠」、「火袋」、「中台」、「柱」、「基礎」、「地覆」の七部構成。寺院に多いのは、春日型・奥の院型・柚木型など。
置き型
基礎や柱などのパーツを省略して発展した小型の灯篭。岬型や草屋型が代表的。
庭園向けに発展した創作型として、雪見型・織部型・勧修寺型・蘭渓型などがあります。灯篭の条件は「火袋があること」なので、形だけ似せたものは道標や置本として分類されることに注意が必要です。

♦石灯籠の産地
灯篭の産地は、古くから優れた石材の採石地でもあります。たとえば、香川県の庵治、愛知県の岡崎、島根県の出雲などは、長い歴史を持つ石材産地で、町全体が石工の伝統を大切に受け継いでいます。
石茂のルーツである、京都の白河という地も、かつては白河石の産地として有名でした。北野天満宮や教王護国寺(東寺)には、今でも「堀川石工芳村茂右衛門」による宮燈篭を見ることができます。
石茂について詳しくは、こちらをご覧ください。
♦灯篭の購入・製作は石茂にご相談ください
石灯籠は、仏教や茶の湯の歴史とともに、日本の石風景を形づくってきました。屋内で何十年、何百年と雨風に耐えながら、人々の暮らしや信仰に寄り添い続けている、日本にとってかかせない存在です。
石灯籠のある風景を楽しみたい、自分だけのオーダーメイドの石灯籠を作りたい、という方は、ぜひ私たちにご相談ください。日本各地の石材産地スタッフと連携し、お客様に最適な石灯籠をご提案します。
石灯篭の製作と販売について詳しくはこちらをご覧ください。